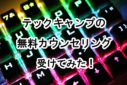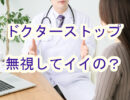就職に有利?人事総務系資格「衛生管理者」のメリット・デメリット
「衛生管理者」という国家資格(免許)がある。
初めて聞いた人は、その名前からして、医療系や食品系の資格と思ったかもしれない。
しかし衛生管理者は、言うなれば人事労務や総務に関連する資格。近しい資格には、社会保険労務士(社労士)などがある。
⇒ 衛生管理者についての詳細はこちら![]() (PR)
(PR)
だから、労働者に対する医学的問診や医療事務をするわけではないし、食品衛生管理者とも違う。労働安全衛生法にもとづいて行う労働者の衛生管理にまつわる事務資格といったところだ。
衛生管理者には第一種と第二種があるが、今回は、特筆しない限り第一種を基軸にして話を進めていく。なお、衛生工学衛生管理者という資格もあるが、やや異質なため、今回は無視する。
<話の流れ>
就職に有利とは言いがたい
就職に有利かどうかは、正直統計データがあるわけではないから断言できない部分がある。
でも私が思うに、衛生管理者の資格があるからといって、特段就職に有利になるとは言いがたい。
その理由は、下記のとおり。
・衛生管理者の国家試験は難関ではなく、希少性が低い
・どうしても衛生管理者が必要なら、在籍中の社員に取得させれば済んでしまう
・特別なスキルの証明にはならない
など。
では、ひとつずつ簡単に説明を進めていこう。
国家試験は非難関で、希少性が低い
衛生管理者の国家試験の合格率は、令和元年度の統計では、第一種が46.8%、第二種が55.2%と、普通レベルといったところ。受験者数は、同統計では、第一種が68,498人、第二種が33,559人であり、まあまあ多い。
そう、難関ではないため、知識のアピールをするにはちょっと弱い。受験者の多さからして合格者もそこそこ多いため、就職活動でライバルに差をつけることを考えたら、十分な力があるとは言いがたい。
既存社員に取得させれば済む
労働安全衛生法上、常時50人以上の労働者がいる事業場には衛生管理者を置かなければならないことになっている。
しかし、その人員を補充するにあたり、わざわざ求人をかける企業はほぼ存在しないだろう。私が実際にハローワークやインターネットで求職活動をしていたとき、衛生管理者を必須資格としている企業はひとつも見かけなかった。
元々在籍している社員に取得させれば済んでしまう話だ。合格率も低くないし、学習時間も1ヶ月~数ヶ月あれば十分なので、既存社員にとって負担も少ない。
特別なスキルの証明にはならない
衛生管理者の資格があるからといって、何か特別なスキルがあるとは判断できない。あくまで、労働安全衛生にかかわる最低限の知識がある、というだけの話だ。
さらに、その知識があるからといって、実務に精通しているわけでもない。50人以上の労働者がいる事業場に必要となる資格者ではあるものの、やはり実務に従事してきた人のほうがスキルがあるのは明白だ。
就職に有利に働くケース
就職に有利とは言いがたいかもしれないが、「無いよりはあったほうが良い」という性質の資格でもある。
たとえば、応募先企業が、偶然衛生管理者を欲していたら、、、。
また、応募先企業の人事担当者があまり資格について詳しくなく、なんとなく資格名だけで「賢そう」と思われる可能性も、ないとは言えない。
それに、全く何も勉強していない人に比べたら、きちんと衛生管理についての勉強をしている人のほうがマシ。勉強することはイイことだ!だから、もしライバルが衛生管理者よりも強い資格を持っていなければ、有利に働く可能性はある。
さらには、あなたがもし何か一つ強い資格を持っているなら、相乗効果を生み出すこともある。たとえば社労士を持っているなら、関連の強い資格だから、より強固になるかもしれない。
とはいえ、基本的には気休め程度と認識しておくのが無難だと思う。
衛生管理者資格のメリット
衛生管理者の資格を持っていることによるメリットは、まあ地味なものである。
・コスパは悪くない
・職場で衛生管理者になれれば、手当がつくことがある
・ほかの資格との相乗効果により、得意分野のアピールになる
では、簡単に説明していこう。
コスパは悪くない
令和2年8月現在、第一種も第二種も、受験料は6,800円。免許証の発行に伴う手続きでも費用はかかる。
でも、総じて1万円もかからない程度。一発合格なら。
その上1ヶ月~数ヶ月の学習で合格できるレベルだし、合格後の免許証発行も、すぐに申請すればすぐにしてもらえるので、時間的な消費も大きくない。
取得によるリターンは小さいかもしれないが、ロスも小さいので、コスパは悪くないといえるだろう。
職場の衛生管理者になれれば、手当がつくことも
職場にもよるが、現場の衛生管理者となることができたら、資格手当がつく可能性もある。中には5,000円、いや、10,000円以上の手当をつけている会社もあるようだ(でも、手当0もざらだろう)。
ただ、資格としての衛生管理者と、実務上の衛生管理者は、やはり別物である。
実務としてきちんとこなすには、試験勉強以上の勉強が必要だし、責任感も必要だ。労働者の健康情報を取り扱う際は、細心の注意を要する。
ほかの資格との相乗効果が期待できる
たとえばだが、衛生管理者と関連性の強い社会保険労務士(社労士)の資格を例にあげよう。
社労士は人事労務資格の代表格であり、その試験範囲は、労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労働保険料徴収法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法 等々である。
で、その中には、衛生管理者の試験範囲とかぶる科目がある。
それは、労働基準法と労働安全衛生法だ。
衛生管理者試験の労働基準法と労働安全衛生法は、社労士試験のそれらほど難しくはない。が、衛生管理者試験では、ほかに医療的・科学的な分野も範囲になっており、そちらは社労士試験の範囲とかぶっていない部分が多い。
つまり、労働安全衛生分野に強い社労士としてアピールしたいなら、衛生管理者の資格は決して無駄にはならないと個人的には思う。
衛生管理者資格のデメリット
一方、デメリットは以下のとおり。
・就職のために取得するようなものではない
・受験には実務経験等が必要
・面接で理由を話すのが難しい
では、簡単に説明していこう。
就職のために取得するようなものではない
会社で「取ってくれ」と言われて受験する人は多いだろう。一方、趣味で取得する人も多そうだ。ネットで調べてみても、資格マニアが興味本位で取っていたりする。
就職のために取得する人も一定数はいるかもしれないが、先述のように、就職に役立つ可能性は高くない気がする(無駄とまでは言わないが)。
受験には実務経験等が必要
衛生管理者試験対策の本をパラパラと見てみると、割ととっつきやすい内容も多く、受験してみたくなる人もいるだろう。
しかし実は、受験には所定の実務経験等が必要となっている。その実務経験がなければ、受験することができず、つまりは実務上の衛生管理者になることもできないということだ。
※ 保健師や薬剤師は、無試験で免許の取得が可能。医師や歯科医師は、衛生管理者免許を取得せずとも衛生管理者になれる。
実務経験については、事業者証明書の下部に書いてある。つまり、実務経験については、社長や支店長や総務部長などの上長に証明をもらう必要があるというわけだ。
で、その証明をもらうのがなかなかめんどくさい。大きな会社とかだと、稟議書からのスタートとなり、いちいち会議を通さないといけないかもしれない。
一方、小さな店とかであれば、店長に「お願~い♪」と頼めば「よっしゃ!がんばってな!」と即座に証明がもらえることもあるだろう。
清掃や整理整頓レベルでも、上長がそれを「実務経験に従事」と判断すれば良い話なので、「自分にはムリだ」とすぐにあきらめないようにしよう。ちなみに、正社員かパートかバイトかとかも特に条件がないので、割とハードルは低い。
面接で理由を話すのが難しい
先ほど申し上げたとおり、衛生管理者は、必要に迫られて取得する人が多い。その「必要」とは、要は、労働安全衛生法上、必ず衛生管理者を置かなければならない状況となっている場合などだ。だから、会社員の場合、好き好んで取得するというよりは、上から言われて取得する場合が多いだろう。
という性質であるものだから、採用面接で「なぜこんな資格を取ったのですか?」と訊かれたら、答えをきちんと準備しておかないと回答に詰まる可能性がある。自己啓発にしては異質な資格だし、就職のためにしては力不足な資格だ。
自分なりにうまく回答できないようであれば、履歴書には書かないのが無難かもしれない。下手に回答したり回答に詰まったりすると、逆効果になってしまう可能性すらある。
以上、衛生管理者の資格についてのお話だった。
私は今、ある程度の大きさのある企業の人事・総務の担当者だが、部署内に衛生管理者はひとりもおらず、全く別の部署にいる保健担当の方が衛生管理者となっている。
まあ、そんなもんさ、世の中。