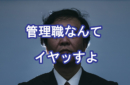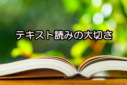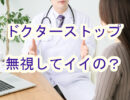社労士オンライン講座「スタディング」を勝手に講評してみた!
社労士試験対策の講座には色々あるが、新しいもののひとつに「STUDYing(以下、スタディング)」がある。
スキマ時間を有効活用するためオンライン講座であり、その価格も、業界内では安価な部類に入る。そうでありながらプロの講義を視聴できて、学習管理ツールもそろっている。効率化の現代では、今後重宝されて然るべき講座かと思う。
⇒ 無料でスタディングを試してみるならこちら![]() (PR)
(PR)
さて、今回の記事では、私が勝手にこのスタディングを講評してみました。
良いことばかり書いてあるサイトもある中、私は本音で語っています。ひととおり最後まで見ていただき、為になれば幸いです。
<話の流れ>
スタディングの3つの特徴
・完全オンライン
・第1回試験からの分析に基づくカリキュラム
・安い
では、解説していきます。
完全オンライン
スマホを使って学習が完結するので、便利であることこの上ないだろう。
行儀は悪いかもしれないが、食事の時間にも学習できる。もちろんトイレでだって風呂でだって電車や信号の待ち時間にだって。
第1回試験からの分析に基づくカリキュラム
50回を超える社労士試験の過去問全てを解くことは、まずもって非現実的だ。しかも、すべて解いたところで合格できるとは限らない。
でも、試験には歴史がある。その歴史の厚みが、今現在の試験を下支えしている。それを考えたら、第1回の試験から分析されたカリキュラムは大変心強いものである。
安い
これはかなり美味しい。
社労士試験の講座はかなり高い。数十万とかするし、中にはあれもこれもとって一年で100万円近く使う人もいる。
しかしスタディングは、2020年9月現在、計10万円もかからない。最も経済的なコースだと計6万円ちょっと(税込で)。アルバイターであってもすぐに回収できる金額だ。
スタディングが合う人
以上3つの特徴を踏まえると、以下の人にオススメできるだろう。
・荷物を極力減らしたい人
・お金の節約が必要な人
・子育てや仕事で忙しい人
・食事中にも勉強したい人
・トイレでも風呂でも勉強したい人
・通勤や移動の時間が長い人
いかにも現代らしい、多忙な人でも学習できる講座かな?と個人的には思う。
スキマ時間は思いのほか多く、食事や通勤の時間に何もできないのはもったいない。個人的には、食事中にサンドイッチを片手に勉強するのは、なんか雰囲気がイイなって思う。
社労士試験ともなれば、年齢層も高めで、仕事に追われて多忙な人も多い。少しでも時間を稼いで学習したいものだ。
スタディングの口コミや評判
一応、口コミや評判についても調査してみたのでご紹介!
どう逆立ちしても予備試験講座も取れるお金が出てこない。かといって独学で何年も時間使えるほど若くもない・・・。労働法務に携わりたいので来年は社労士受けます。社労士24、フォーサイト、スタディング。値段的にここらが限界。スタディングの講師、無名かと思ったら辰巳にいたんだ・・・。
— MO@資格試験アカウント (@MONSHIKAKU) October 20, 2019
レジに並びながら社労士の問題演習
最近の通信教育はとても使いやすい
隙間時間で勉強ができるとは!#社労士 #自己啓発 #スタディング #隙間時間— かずよし (@BetterLifeBe) June 15, 2020
2021年社労士受験に向けていろいろ情報収集してる!
業務でなかなか定時上がり出来ないから通信講座やりたいな〜と思いつつ、なにが最適か悩み中
気になるのは社労士24とフォーサイト!あとスタディングも惹かれる…!悩む!— ポン酢@社労士受験 (@bpIza8NVmUxbCXF) August 25, 2020
なお、他の試験の講座に目を向けたら、こんな声があった。
スタディング
税理士試験までやってる。
金額も大手の数分の1。
基礎はこれで直前期に大手の大原かTACをプラスしたらいいじゃん。
社労士試験終わったら色々考えよー。— yuki 社労士受験垢 (@E1gThQsoQZa2T7G) September 6, 2020
スタディングの宅建士講座
権利関係まで見終わりました!
一つの講義を見終わったらすぐに問題を解いてアウトプット学習ができるところが良いところ
もう少しで一通り全て講義は見終わるので、その後の学習方法も考えないと。
でも動画でインプット学習できるって素敵✨令和の学び方かな✨
— さんご@ブログで飯が食えるようになりました (@sango_work) July 28, 2020
それにしても、スタディングだけで司法試験まで行けちゃう人って、いるのかな。。。
— (@usamimix) January 7, 2020
という感じだ。
公式サイト見ると、スタディングを利用して、司法試験に受かった人、税理士試験に受かった人、宅建士試験に受かった人の声もある。
スタディングの気になる点
・紙媒体での学習ができない
・新興講座である
・知名度が低い
以上の3つについて、解説してみたいと思う。
紙媒体での学習ができない
完全オンラインのデメリットは、紙媒体での学習ができない点。
なので、ペン等を使ってアナログな書き込みをしたい人には向かないだろう。
あと、スタディングを利用するにしても、試験が近づいてきたら、別に紙媒体でも慣れておくのがオススメ。なぜなら、本番は所詮紙媒体だから。
新興講座である
スタディング自体は10年以上の歴史があるみたい。
しかし、社労士講座は第52回(2020年度)の試験対策からスタートしたばかりなので、口コミや評判は少ない。だから先ほどの口コミでも、紹介できるものが少なかった。
だからといって、良い・悪いだけは分からない。
もしスタディングに全てをゆだねるのが怖いなら、サブツールとして利用する方法もあると思う。間違いなく言えるのは、効率化を図るには良い教材だと思う。なにより時間は有限なのだ。
知名度が低い
社労士試験の講座といえば、大原とかTACとかLECとかクレアールとかアガルートとか・・・。
そのあたりの予備校は知名度が高いが、スタディングはそれほど噂を聞かない。というのも、先述のとおり社労士試験の講座が新しいのが原因だろう。これから徐々に知名度が上がってくるものと思う。
また、この講座がどういう成果を残していくのかも興味深い。
知名度が低いと、仲間が少なかったり、情報共有できる場が限られてきたりする。そういうのは、やはり大手の予備校は強い。
でも私は、通信講座すらやらず、完全独学で社労士試験に合格できた。なので、仲間が必要でないとダメとか、予備校に通わないとダメとか、そういうのは関係ないと思う。
なによりも、
・どん欲でひたむきな学習態度
・根拠のない自信
・学習の効率化
・・・これらさえあればどんなツールでも良いと思う。極論すれば、この多忙な世の中、かつ、新型コロナの懸念もある中、通学で受講するというのは正直古くて効率が悪い。
というわけで
少し長くなってしまったが、スタディングについての所感でした。
学習を効率化したい人に良い講座だと思う。とにかくオンラインで完結できて安上がりなので、コスパが良い。迷っているくらいなら始めてみてはいかがでしょうか。時間は有限なのだから!
⇒ 無料でスタディングを試してみるならこちら![]()
![]()
![]()
![]()