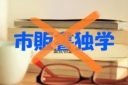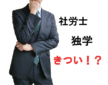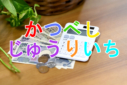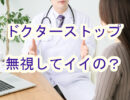社労士になりたいなら、社労士受験をやめたほうがいいかもしれない理由
社労士試験に受かろうと頑張っている人は多いと思う。私もそうだった。
社労士試験に受かって、早く社労士になって活躍したい!みんなから尊敬されたい!人々を助けたい!
・・・そう思って勉強している人は少なくないだろう。
しかし今回、あえて人の夢に水を差すことになるかと思うが、批判を恐れず、ひとつ大きなサインを送りたい。
タイトルのとおり、
社労士になりたいなら、社労士試験の受験をやめたほうがいいかもしれない。
・・・こう書くと社労士会や連合会から怒られそうだが、悪いことは言わない。再度検討し直していただきたいのだ。
では、なぜ、社労士になりたいなら受験をやめたほうが良いのか、その理由を以下で述べたいと思う。実は、科学的にも説明がつくのだ。
まず前提として、仕事観には次の2つがある(『科学的な適職![]() (PR)』(著:鈴木祐) から引用)。
(PR)』(著:鈴木祐) から引用)。
| ・適合派:「好きなことを仕事にするのが幸せだ」と考えるタイプ。「給料が安くても満足できる仕事をしたい」と答える傾向が強い ・成長派:「仕事は続けるうちに好きになるものだ」と考えるタイプ。「そんなに仕事は楽しくなくてもいいけど給料は欲しい」と答える傾向が強い |
この仕事観について、2015年、ミシガン州立大学はアンケートをとって追究した。
そしたら驚きの結果が分かったのだ。
なんと、どちらも幸福度は変わらなかったという。
むしろ、長い目で見ると、成長派のほうが幸福度が高かったとか。
『科学的な適職![]()
![]()
一見、適合派のほうが幸せになれそうに見えます。自分が情熱を持てる仕事に就けば毎日が楽しく、金目当てに働くよりも人生の満足度は高まりそうな気がするでしょう。
ところが、結果は意外なものでした。適合派の幸福度が高いのは最初だけで、1〜5年の長いスパンで見た場合、両者の幸福度・年収・キャリアなどのレベルは成長派のほうが高かったからです。
話はこれで終わらない。
オックスフォード大学の研究チームは、3つのグループに分けて、仕事の継続率を調べた。
その3つのグループは以下のとおり(『科学的な適職![]()
![]()
| ・好きを仕事に派:「自分はこの仕事が大好きだ!」と感じながら仕事に取り組むタイプ ・情熱派:「この仕事で社会に貢献するのだ!」と思いながら仕事に取り組むタイプ ・割り切り派:「仕事は仕事」と割り切って日々の業務に取り組むタイプ |
さあどうなったか。
結果はもう想像に難くないと思うが、割り切り派の継続率が最も高く、逆に、好きを仕事に派は離職率が高かったそうだ。スキル面についても、割り切り派が最も優秀だったらしい。
これらを社労士バージョンに置き換えてみると、「私は社労士になりたい!」とか「社労士の勉強は楽しいから、これを仕事にしたい!」と思っている人ほど、いざその仕事に就いたときに辞めがちってわけだ。
「何をそんな!こんなに情熱を持っているのに!」と叫びたくなると思うが、よく考えてみれば、たしかに納得できる。
好きという感情は、実に不安定なものだ。今から10年前に持っていた好みや趣味は、今も全く変わらずに持ち続けていますか?と、自問自答してみてはどうだろう。
きっと、多くの人が「違うかも」とか「たしかに趣向が変わってきた」と答えるはずだ。
そう考えたら、今持っている好みを、10年後にも持っている保証はどこにもないと気づく。
また、今実際に思い描いている社労士像は、現実の社労士と同じだろうか。スーパーマンみたいな社労士が身近にいるなら憧れるかもしれないが、果たして、現実と理想のギャップに直面しても、幸福度を下げずに社労士業を楽しめる自信はあるだろうか?
・・・そう、だから、「社労士になりたい!」と思っている人こそ、本当に社労士試験を受ける意義があるのかどうか、もう一度よく考えたほうが良いと思う。
あまり希望を大きく持つと、いざギャップに出くわしたときに、モチベーションや幸福度が低下してしまうのだ。
自己啓発のためとか、人生の知識を増やすためとか、単に合格することが目的にすぎないとか、趣味とかなら、無理にやめる必要はないだろう。が、なにせ時間と労力とお金がかかる試験だ。しかも、一度やり始めると、「せっかくここまで来たんだから」と後に引けなくなる可能性もあり、ただただ自分を正当化するために受験することにもなりかねない。
なので、考え直してみてください。
とはいえ、社労士の場合、先ほどの3つのタイプのうちの割り切り派は、なかなか存在しないんじゃないか?とも思う。
もう一度3つのタイプをあげてみよう。
| ・好きを仕事に派:「自分はこの仕事が大好きだ!」と感じながら仕事に取り組むタイプ ・情熱派:「この仕事で社会に貢献するのだ!」と思いながら仕事に取り組むタイプ ・割り切り派:「仕事は仕事」と割り切って日々の業務に取り組むタイプ |
割り切って社労士になる人は、そうそういないだろう。だって、そもそも難しい資格試験を受験する以上、何らかの動機やモチベーションが前提としてあるから。
もし何とな〜く社労士になる人がいるとすれば、こんな人。
まず、社労士関係なくとにかく勉強自体が好きで受かっちゃった人。こういう勉強自体が好きな人は、別に社労士じゃなくて良く、偶然そこに社労士があったから選んだにすぎない。
また、何らかの原因により割り切って社労士になる人。たとえば、会社からの命令だったり、親の後継ぎだったり、利権絡みだったり、人生のドン底から這い上がるためだったり、得体の知れぬ使命感だったり…。こういう人もまた、心の底から社労士になりたくてなっているわけではないかもしれない。追いつめられてなっている可能性もある。
あと、社労士資格を使って金を荒稼ぎしている人も、人生において偶然そこに社労士があったからそれを選んだだけに過ぎないかもしれない。「社労士になりたい」とか「社会保険分野じゃないとダメなんだ」と、本当に受験初期の頃から思っていただろうか?人助けをしたいなら、すぐに介護施設とかに就職したほうが早いじゃんか?
・・・さて、社労士試験に合格したいと考えている人をディスる形となってしまったが、私の本心を言うと、やっぱり「社労士になりたい」「人助けをしたい」と思っている人こそ、社労士として活躍してほしいと願っている。
不純な動機ではなく、純粋で情熱的な動機を持っている人のほうが、正義を追い求めるだろうし、社労士としての良きプライドを持つだろうから。
でも!!
科学的には、それは理想論なのかもしれないのだ。
綺麗事が好きな私は、理想どおりであることを願うばかり。だけど、先ほどの話のとおり、現実には嫌なこともあるし、思い通りにならないこともあるし、描いていた像と異なることもあって当然。
この世の中にはブラック企業や悪いことを考える経営者が多いが、社労士はそういう人を主なお客さんとする。たとえホワイトであっても、やはり経営者の思いに寄り添って仕事をしなければならないので、なかなか思い通りにはいかないし、常に法律に忠実に従えるとも分からない。
そういった現実に打ち勝てれば良いのだが、人間同士の営みである以上は、必ずどこかで軋轢が生まれ、少なからず苦しさを覚えることになる。
その苦しさを乗り越えられるか?がカギだが、こういうのは、何とな〜く仕事をしている人のほうが案外強い。変に期待をしないからね。
・・・で、最後に申し上げると、社労士になりたかったり社労士事務所に就職したりしたいなら、とりあえずは、やってみるのも良いと思う。
どのみち未来なんて分かりゃしないもん。
好きを仕事に派 も、別に完全に全員が離職しやすいといわけではなく、一部の人はやはり続いていくはず。
で、「やっぱ違う」と思ったら、そのときに辞めればいい。ああだこうだ悩む前に、次の仕事を探せば良いのだ。
以上、長くなってしまったが、とにかく、人それぞれで答えは違うはず。未来のことを考えすぎてもラチが明かないので、早いところ今納得できる行動をとっていきたいものだ。
社労士業に夢を持って頑張れる自分がいるなら、別に今勉強をやめる必要はない!というのが、科学を無視した個人的見解。
そして世の中の社労士の先輩方は、熱意ある後輩がやめないように、社労士界の良さをたくさん伝え、ポジティブな思いで背中を押していってくださいますと幸いです。